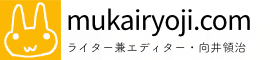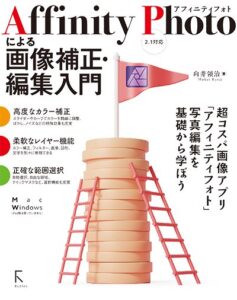七つ道具 ③ATOK|標準の追求

ぼくの仕事の「七つ道具」、3つめは「ATOK」だ。なお、ここで扱っている機能の多くは、WindowsとMacのみでのものである。商業ベースのレビュー記事ではないので、原則としてOSごとの対応状況は細かく記述していない。
ATOKとは
「ATOK」とは、ジャストシステム社製の日本語入力プログラムで、Windows版、Mac版、Android版、iOS/iPadOS版がある。現在は買い切りの製品は終了し、月間または年間契約の「ATOK Passport」を契約して利用することになっている。ただし、年間契約しても割引はない。
→「ATOK Passport」(ジャストシステム)
ATOK Passportには、月間300円の「ベーシック」と、月間600円の「プレミアム」の2つのコースがあり、後者では、①iOS/iPadOS版、②オンラインで引けるクラウド辞書、などが利用できる。
なぜATOKか
日本語入力プログラムなぞいまやOSについてくる代物だし、商売で原稿を書いている方でもこれで十分だという向きも多いだろう。逆に言えば、変換性能や一般的な辞書の語彙は、日本語入力プログラムというジャンルとしてそれくらい完成されてきたと言える。
それでもぼくがお金を出してATOKを使っている最大の理由は、ぼくのジャンルで必要な日本語の文章を入力するプログラムとして、もっとも信頼できると思っているからだ。それには、辞書に関連する2つの大きな理由と、いくつかの小さな理由がある。
1つめの理由・広辞苑
1つめの大きな理由は、信頼できるたくさんの辞書を、原稿を書きながら速やかに引けることだ。
いまどき信頼できる国語辞典もWebなら無料で使える時代だが、文章を書きながら、つまり、入力した語句を変換しながら辞書を引けるのは効率が格段に違う。自分の文章だけに集中できるし、気を散らす広告を見る必要もない。
辞書のウインドウを開いたり、別の辞書へ切り替えたりする操作は、キーボードからのショートカットで実行できる。つまり、辞書を引くためにキーボードから手を離さずに済む。これは、思考に割り込みが発生しないということだ。集中して長い文章を書くときには重要なことである。

ATOK Passportのプレミアム版では、国語辞典だけでも広辞苑と大辞林の2つが使える。また、プレミアムとベーシックのいずれでも、別売のオプション辞書を併用できる。国語辞典としては、広辞苑、大辞林、明鏡、ほかに角川類語もある。こちらは買い切り制だ。
→「オプション辞書の一覧」
なお、ATOK Passportの辞書はオンラインで提供されるので、オフラインでは利用できない。オプション辞書版はオフラインで利用できる。同じ広辞苑でもそういった違いがある。
広辞苑について
いったん横道へそれて、ぼくにとっての広辞苑の位置づけについて触れておく。
ぼくとしては、信頼に足る文章を書くなら、まず広辞苑は必須であると考えている。別に広辞苑が飛び抜けて優れているとは思っていないし、それ1つあれば済むとも思っていない。それでも国語辞典といえば広辞苑が代表的であることは確かだろうし、広辞苑を引かずに結論を出してもいけないと思う。できるだけ広く通じる文章のために「標準」を強く意識しておきたいのだ。辞書というもの自体が言葉の「標準」だが、広辞苑は「標準の標準」と呼んでもよいだろう。
自分の言葉だけで文章を書ける職業であれば、とくに広辞苑にこだわる必要はないはずだ。ひところ新明解が流行したように、クセがあっても好きな辞書だけを使う道もある。もちろん一般的には小説家やエッセイストこそ辞書を引きまくる職業だが、いざとなれば「私はこう書きますから」と言うこともできるだろう(ぼくはそういう書き方の文章を商業で書いたことがないので推測である)。
しかし請負のライターはそんなことを言って編集者の手間を増やすわけにはいかない。言葉の選び方自体が表現となるジャンルであればともかく、ぼくのジャンルでは文学性など不要だし、むしろ排除すべきと思っている。
ちなみに、macOSやiOSにはスーパー大辞林が内蔵されていて、変換途中の言葉を辞書で引いてくれる(かつてEncartaというタイトルを持っていたMicrosoftがWindowsに辞書を内蔵してくれないのはなぜだろう)。また、物書堂の日本語入力プログラム「かわせみ」も、バージョン4から「辞書by物書堂」を使った検索ができるようになった。しかし、ぼくの仕事としては、まず広辞苑がほしいのである。
2つめの理由・共同通信社記者ハンドブック
さて、2つめの理由は、「共同通信社記者ハンドブック」(以下「記者ハン」)が引けることだ。これはATOK Passportのサービスには入っていないので、別途購入してインストールする必要がある。
→「共同通信社 記者ハンドブック辞書 第14版 for ATOK」
たとえば「30年にわたる」と書くとき、本来は「亘る」と書くようだが、広辞苑には「渡る」の項目の中で「(「亘る」とも書く)」と書いてある(ということは、「亘る」と書いてもよいということだ)。それ以外の国語辞典を読んでも、「渡る」と書いてよさそうに思える。
しかし記者ハンによれば「わたる」と書くべし、となっている。「亘」は常用漢字ではないので開けということのようだ。ATOKでは変換中に「《記:注》」という但し書きで示し、辞書ウインドウを開けば使い分けも教えてくれる。

ぼくも記者ハン原理主義者ではないので、企画によっては「渡る」だとか「亘る」と書いてもかまわないと思う。しかし、記者ハンで「わたる」が標準とされていることにも相応の理由がある。それを知らずに「渡る」と書くのか、知った上で「渡る」と書くのか、あるいはやはり従って「わたる」と書くのか、すべてを振り切って「亘る」と書くのか。その判断が踏まえるところが異なってくる。
実際、ぼくが編集業で扱う原稿では、企画によって判断を分ける必要がある例の1つが「繋ぐ」である。「繋」は常用漢字ではないので、記者ハンでは「つなぐ」となっている。だから「開発者とメーカーをつなぐ」くらいであればひらがなにする。しかしネットワーク系の原稿では頻出するので「サーバーとクライアントを繋ぐ」とすることにしている。
こういった標準(判断基準)を確かめたうえで選択をするわけだが、それらの作業をかな漢字変換の作業の中で済ませられる。他人の原稿を扱う場合でも、後述の「ATOKイミクル」を使ってすぐに検索できる。これは大変効率的だ。
それ以外の理由
ほかにもいくつかの理由がある。
たとえば、漢字の送り仮名を本則に限定する設定がある。「おこなう」の本則は「行なう」ではなく「行う」である。「行なう」と書く方も時折見かけるし、その気持ちもわかる。常用漢字表でも、「行なう」を許容するとされている。しかし、本則が「行う」である以上、自分が扱う原稿では「行う」としている。ATOKでは環境設定で本則に限定できるので、うっかり「行なう」を選んでしまう心配がない。

商品名や登録商標の指摘もしてくれる。広告系の記事の仕事では書けないので、うっかり「セロテープ」と書いても指摘してくれる。
変換候補ウインドウから候補を選ぶとき、たいていは数字キーを使うようになっているが、ATOKではアルファベットキーを使うように変更できる。ローマ字入力でも数字キーの行まで指を移動しなくて済む。
オプションのものを含めて、辞書は独立した辞書引きアプリとして動作する「ATOKイミクル」からも利用できる。確定済みの文字列を使った辞書引きも可能だ。つまり、広辞苑や記者ハンを独立した辞書として使えるのだ。記者ハンは電子書籍版も発売されているが、「アプリを切り替えて、記者ハンを開いて、本文検索して」という作業がごくわずかな手間と時間で済む。

付論
七つ道具として「辞書by物書堂」とATOKを挙げたが、両者はちょうど補完しあう関係になるので、両方ともよく使っている。具体的には、WindowsではATOK、iPhoneやiPadでは「辞書by物書堂」、Macでは両方を使える。仕事ではATOKに買った辞書が使えれば十分だし、スクリーンショットに写っているもの以外の辞書も使っているし、編集の仕事はWordを使う必要があるので、編集の仕事はWindowsでやっている。自分の原稿はMacで書いてもいいのだが、Just Right!や一太郎を通すために、いまや結局Windowsを使うことが多い。
そもそもかな漢字変換の性能自体は、よほど高望みをしない限り、もはやどれも大差ないように思える。このシリーズの記事を書いて気づいたが、そのなかでATOKを選ぶポイントは、やはり辞書だった。
もう1つぼくにとって重要なのは、まだまだタブレットやスマホではほとんどの仕事ができないことだ。
まず、iOSとiPadOSでは相変わらずATOKを外付けキーボードで使えないので、自分の原稿は書けない。これはAppleのセキュリティ対策の方針が理由のようだが、もうそろそろなんとかしてほしい。
Androidは外付けキーボードでATOKが使える。実際、iPadを持っているにも関わらずAndroidタブレットを買ったのは、それが理由だった。「ATOKイミクル」に相当する独立した辞書アプリはないが、ATOK Passportのプレミアムであれば変換中に辞書が引ける。
しかし、iOS、iPadOS、Androidのいずれでもではオプション辞書をインストールできないので、記者ハンが利用できない。日常的な文章はともかく、ぼくがiPadやAndroidで仕事の原稿を書かないのは、これが理由である。
ところで、ぼくの原稿は翻訳くさいと言われることがあるが、熟語や故事成句を極力使わないことが理由だろうと思う。そういった言葉は人によっては知らなかったり、主旨を誤解していたりするとよく言われる。先日も「失笑」という言葉の誤用が広まっているというニュースを見た。ATOKでは辞書とは関係なく、誤用が多い単語は「使い方に注意」と表示し、「校正支援解説」という機能で教えてくれる。

そういう単語が必要なジャンルであれば確かに悩ましい話だと思うが、ぼくのジャンルに限れば「そもそも使わなければよい」というのがぼくの立場である。
よって、漢字はもっぱら常用漢字のみを使うことにしているし、成句もまず使わない。「業界の嚆矢となった」「猖獗をきわめている」などと書かなくても、「製品としては最初のもの」「一般には誤解されていることが多い」のように書けば間違いなく伝わるし、書くときに悩む必要もない。むしろ、意図するところがはっきりする。著者の教養を開陳――ではなく、ひけらかしたいのであれば、実用書ではないところでやればよい。書き方のルールは1つではないので、同じジャンルに異なる方針の方がいてもまったくかまわないが、少なくともぼくはそのようにやらせてもらっている。